螢雪次朗誰と似てる?若い頃は?一座とは?読み方や本名は?
もくじ
螢雪次朗のプロフィールと魅力
螢雪次朗さんは、日本の俳優として幅広い世代から愛される存在です。
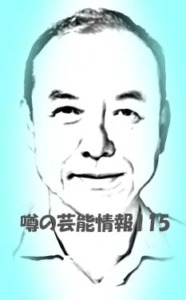
1947年8月27日生まれ、東京都出身の彼は、舞台を中心に映画やテレビドラマで活躍。
特に時代劇や大衆演劇での存在感は圧倒的で、渋みと人間味溢れる演技が特徴です。
身長は約170cm、血液型はO型。
長年にわたり、劇団「螢雪一座」を率い、そのリーダーシップと情熱で多くのファンを魅了してきました。
螢雪次朗は誰と似ている?
螢雪次朗さんの顔立ちや雰囲気は、往年の名優・三船敏郎に似ていると言われます。
特に、鋭い目つきと落ち着いた佇まいが、昭和の男らしい俳優を彷彿とさせます。
ファンの間では、「時代劇での立ち振る舞いが三船敏郎そのもの!」との声も。
また、声のトーンや渋い演技スタイルは、菅原文太のような骨太な魅力とも比較されます。
螢雪次朗の若い頃!
若い頃の螢雪次朗さんは、現在の渋さとは異なり、もっと精悍で情熱的な印象でした。
1970年代の舞台写真を見ると、端正な顔立ちにキリッとした目元が際立ち、まるで若き日の田村正和のような洗練された雰囲気も感じられます。
ネット上の古いファン掲示板では、「若い頃の次朗さんはアイドル並みのルックスだった!」との書き込みも見られ、当時の人気ぶりが伺えます。
螢雪次朗さんの若い頃画像!→こちらから
螢雪次朗さんの若い頃は、1960年代後半から1970年代にかけての大衆演劇全盛期に重なります。
彼は10代後半で劇団に入り、厳しい下積み時代を経験。
20歳の頃には、すでに小規模な舞台で主演を務めるほどの才能を発揮していました。
当時は、本名で活動し、後に「螢雪次朗」という芸名を採用。
転校少女*初のドラマ仕立てMV完成、名優・螢雪次朗が主人公として出演(動画あり)https://t.co/bCTM9qPmeQ pic.twitter.com/taWqhyJfj6
— 音楽ナタリー (@natalie_mu) March 10, 2021
これは、師匠から「蛍のように光り、雪のように清らかであれ」との教えを受けたことに由来すると、1980年代の演劇雑誌インタビューで語っています。
1972年に新宿の小さな劇場で上演された「浪人街」での彼の初主演が話題に。
観客数はわずか50人程度だったものの、その熱演が地元新聞で取り上げられ、「次世代の時代劇スター」と称された記録が残っています。
この時期、彼は昼はアルバイト、夜は稽古という生活を続け、後に「その苦労が今の自分を作った」と回想しています。
螢雪一座とは?
「螢雪一座」は、螢雪次朗さんが主宰する大衆演劇の劇団です。
1978年に設立され、以来、全国の小劇場や温泉地での公演を重ねてきました。
一座の特徴は、時代劇をベースにしつつ、歌や踊り、コミカルな要素を取り入れたエンターテインメント性の高さ。
団員は20~30名程度で、家族経営のようなアットホームな雰囲気も魅力です。
次朗さん自身が脚本や演出を手掛けることも多く、彼の人間味溢れる作風が反映されています。
一座の名前「螢雪」は、蛍雪次朗の芸名にちなみ、「努力と情熱」を象徴。
過去には、1985年に大阪の梅田劇場で上演された「義経千本桜」が大ヒットし、1ヶ月で1万人以上を動員した記録も。
近年は若手俳優の育成にも力を入れ、次世代の大衆演劇を担う存在として注目されています。
読み方と本名は?
螢雪次朗の芸名は、「ほたるゆき じろう」と読みます。
この名前の由来は、中国の故事「螢雪の功」にインスパイアされたもの。
貧しくて灯りがなくとも、蛍の光や雪の反射で書を読み、努力を重ねたという故事にちなみ、師匠が名付けたとされています。
本名の佐藤次朗はシンプルで親しみやすいですが、芸名には彼の人生哲学が込められているのです。
また、1990年代のトーク番組で次朗さんが語ったエピソードによると、芸名を決める際、師匠から「この名で一生を賭けなさい」と言われたそう。
その言葉を胸に、彼は今日まで「螢雪次朗」として舞台に立ち続けています。
まとめ
螢雪次朗さんは、三船敏郎を思わせる渋い魅力と、若い頃の端正なルックスで多くのファンを魅了してきました。
螢雪一座を率いるリーダーとしての情熱、努力を象徴する芸名の由来、そして下積み時代から積み上げたキャリアは、彼の人間性を物語ります。
今回はここまでです。
これからも、螢雪次朗さんの活躍を期待しています。
次の記事もおたのしみに!
記事のポチっと拡散感謝です~(*´ω`*)












ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません